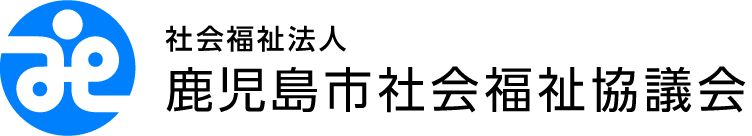鹿児島市成年後見センターのご案内
成年後見センターでは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった人(本人)が、地域で自分らしく安心して暮らせるように「成年後見制度」に関する相談や、制度の利用支援を行っています。
お気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
成年後見制度に関する相談・手続の支援
- 相談員による相談
成年後見センターの相談員が、成年後見制度の説明や利用手続などの相談に、電話・面談・訪問で応じます。(来所相談の日時の事前連絡を承っております。)
-
- 相談場所 鹿児島市成年後見センター(かごしま市民福祉プラザ4階 )
- 相談時間 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話相談 ☎ 099-210-7073
- 専門職による相談(専門家によるアドバイス)
法律的な知識や判断が必要な成年後見制度に関する相談について、弁護士又は司法書士が面談で応じます。
事前に相談員が相談内容をお伺いし、専門相談が必要と認められる方について予約を受け付け、日時を決めて成年後見センターに来ていただきます。
-
- 相談場所 鹿児島市成年後見センター(かごしま市民福祉プラザ4階)
- 相談時間 第2・4火曜日 午後2時から午後4時まで(要予約)
- 対 象 相談員による相談で予約をされた方が対象です。
成年後見制度の広報啓発
成年後見制度をより多くの皆様に知っていただくため、講座等を開催します。
また、市民の皆様がさまざまな集まりで開催される成年後見制度の勉強会・研修会等を開催される場合に、センターの相談員が会場に出向き、制度に関する説明を行います。
開所日時
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝・休日、12月29日~1月3日は休み)
連絡先
TEL 099-210-7073 (直通)
FAX 099-210-7103
所在地
〒892-0816
鹿児島市山下町15番1号 かごしま市民福祉プラザ4階
※鹿児島市成年後見センターは、鹿児島市から委託を受けて、鹿児島市社会福祉協議会が運営しています。


アクセス
- 市電「市役所前」下車 徒歩4分、市電「水族館口」下車 徒歩4分
- JR「鹿児島駅」下車 徒歩10分
- バス「市役所前」下車 徒歩5分、「水族館口」下車 徒歩3分
※ 駐車場は、かごしま市民福祉プラザ地階駐車場をご利用ください。
成年後見制度とは?
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人(本人)は、預貯金などの管理や介護サービスの契約などを自分ですることが難しくなる場合があります。
また、自分に不利な契約を結んでしまうなど、消費者被害にあう恐れもあります。そのような時、生活や権利を守り、地域で自分らしく安心して 暮らせるように支援するのが、『成年後見制度』です。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立て(手続き)をする必要があります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分になった人が、財産管理や、医療・福祉等のサービスについての契約を行うことを支援してもらう制度です。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が支援します。
任意後見制度
今は大丈夫でも、将来の不安に備えて、あらかじめ支援してもらう人(任意後見人)と、支援してもらう内容を決めておく制度です。
あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざというときの財産管理や、療養看護に関する契約の代理権を与える(同意・取消権は与えられません)任意後見契約を、公証人が作成する公正証書で結んでおきます。
制度の利用のしかた
相談
本人や親族、支援者など、お気軽に成年後見センターにご相談ください。
成年後見センターの相談員が事情をお伺いします。また、法律的な知識や判断が必要な相談については、予約制で弁護士や司法書士の専門職に相談することができます。(相談料無料)
申立書類の準備(申立書類)
- 申立てが必要な場合は、申立書の内容を説明します。
- 本人の判断能力を確認するため、医師の診断を受ける必要があります。
- 申立書や診断書は定められた様式があります。(申立書の作成を弁護士、司法書士に依頼する場合は有料となります。)
家庭裁判所への申立て
|
本人・配偶者・4親等内の親族 |
|
原則として本人の生活の本拠地(日常生活をしている所)を管轄する家庭裁判所に行います。 |
審判手続き
- 調査・・・家庭裁判所の調査官が、本人や親族などに事情を尋ねたり、問合せをしたりします。
- 鑑定・・・必要に応じて、本人の判断能力について医師による鑑定を行うことがあります。
審判
- 家庭裁判所は後見などの開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる成年後見人などや監督人を選任します
- 審判内容が法務局に登記されます。審判内容は戸籍には記載されません。
申立てから審判まで2か月ほどかかります。
成年後見制度に関するお問い合わせ先
成年後見制度を利用するための申立手続きや必要書類、費用などについて
| 鹿児島家庭裁判所 | ☎ 808-3724 |
|---|
相談窓口
「成年後見制度」・「任意後見契約」の内容等については、下記の専門家の相談窓口があります。(相談は予約が必要な場合もありますので、必ず事前に電話等でお問い合わせください。)
| (公社)成年後見センター・リーガルサポート鹿児島支部 (鹿児島県司法書士会) |
☎ 248-8860 |
|---|---|
| 権利擁護センターぱあとなあ鹿児島 (鹿児島県社会福祉士会) |
☎ 213-4055 |
| 鹿児島県弁護士会 | ☎ 226-3765 |
| コスモス成年後見サポートセンター (鹿児島県行政書士会) |
☎ 253-6500 |
| 鹿児島公証人合同役場 | ☎ 222-2817 |
身寄りがいない等の理由により、制度利用の申立てをできる人がいない場合は、市役所各担 当課までお問い合わせください。
| 認知症高齢者 | 認知症支援室 | ☎ 808-2805 |
|---|---|---|
| 知的障害者 | 障害福祉課 | ☎ 216-1272 |
| 精神障害者 | 保健支援課 | ☎ 803-6929 |